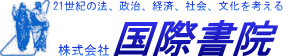理由ある欲望 雑誌『中国青年』からみる中国社会の階層上昇志向

改革開放以降、人々はどのような上昇志向をもっていたのか。また各時代の公的文化装置はどのような様相を示していたのかを考察することによって、人々は自分自身の社会的位置づけに直面したのか、探求する。(2025.5.1)
定価 (本体9,000円 + 税)
ISBN978-4-87791-332-8 C3031 613頁
- 第一部
- 序章 理由のある欲望
-
- 1 「欲望の氾濫」という道徳的な見地に立脚する批判的な見方
- 2 理由ある欲望という理解的な立場の可能性
- 3 公的文化装置の論理と生活世界の論理
- 4 研究目的:二つの理解
- 5 研究方法と研究枠組
-
- 第1章 改革開放以降の中国の上昇志向に近づくための先行研究
- 第1節 改革開放後の社会意識の変化に関する研究
- 1 若者(青年)価値観の視点からの意識研究
- 2 伝統から近代へという「社会転型」の視点からの意識研究
- 3 先行研究の考察
- 第2節 80年と90年代以降の中国社会の文化的状況の変化に関する研究
- 1 80年代と90年代との文化的状況の違い
- 2 「現代化」と名乗る文化装置による統制の80年代と「衆神狂歓」の90年代
- 第3節 90年代以降の社会的文化的状況に関する研究
- 1 「新イデオロギー」説──「エリート知識人」の視点
- 2 「欲望弁証法」──「欲望」をキーワードとした近代社会批判
- 3 「チャイナ・ドリーム」説
- 4 小結
- 第4節 階層意識研究の成果紹介
- 1 階層意識研究での主な既存研究
- 2 階層意識研究の考察
- 第5節 上昇志向に関する先行研究
- 第6節 先行研究の考察
- 第1節 改革開放後の社会意識の変化に関する研究
- 第2章 研究資料としての『中国青年』雑誌
- 第1節 中国の雑誌業界の状況から見た『中国青年』
- 1 中国雑誌業の規模と分類
- 2 中国の雑誌業全体の特徴
- 3 政府の条例による雑誌への統制の変化
- 4 市場化の過程
- 5 青年雑誌の歴史的変容
- 6 『中国青年』の社会的影響力の変化
- 第2節 資料としての『中国青年』の利用方法
- 1 『中国青年』の読者投書の内容の変化
- 2 本研究における「読者の声」の選定と使用方法
- 3 読者の声とする資料の分類
- 第1節 中国の雑誌業界の状況から見た『中国青年』
- 第3章 改革開放以降の経済発展と社会変動
- 第1節 本研究で採用する三つの時代区分
- 第2節 1978年以降の社会経済変動
- 1 1978年以降の社会経済変動
- 2 改革開放以降の所得格差
- 3 1978年以降の教育の発展及び制度的不均衡
- 4 社会階層構造の変容
- 第4章 公的文化装置による中国社会の語られ方の変容
- 第1節 雑誌『中国青年』のプロフィール及び先行研究
- 1 『中国青年』のプロフィール
- 2 『中国青年』を含む中国雑誌を対象とした先行研究
- 3 サンプルの選定理由について
- 第2節 周年記念の内容から見る雑誌の自己認識の変化
- 1 政治的価値の表明
- 2 読者の承認による価値の定義への移り変わり
- 3 歴史あるユニークなメディアとしての雑誌の価値の表明
- 第3節 三回の改版に見られる若者との位置関係の変化
- 1 政治的権威を背景とする指導的・教化的な立場──1995改版以前
- 2 迎合と教化との間の不自然さ──1995年一回目の改版
- 3 「奮闘」の過程そのものの重視──2003年二回目の改版
- 4 「奮闘」の結果の重視──2008年三回目の改版
- 5 『中国青年』の三回改版の社会学的意味
- 第4節『中国青年』雑誌に見る中国社会の語られ方の変化
- 第1節 雑誌『中国青年』のプロフィール及び先行研究
- 序章 理由のある欲望
- 第二部
- 第5章 教育達成による上昇移動への熱望(1978−1984年)
- 第1節 1978−1984年における社会経済変動
- 1 大学入試制度の再開と知識重視の風潮の発生
- 2 知識青年の「返城」による失業の大量発生及び就業形態の変化
- 3 70年代末から80年代初頭の階層構造
- 4 小結
- 第2節 「登竜門」とされる大学受験:学業に関する読者の声
- 1 学習効率を上げる方法や受験の注意点などノウハウ型の投書
- 2 大学受験に対する受験生の不安や焦燥感
- 3 大学入試の競争激化による中高生のしわ寄せ
- 4 小結
- 第3節 職業による社会的地位の不安:職業に関する読者の声の分析
- 1 職業に関する悩みから見る階層ヒエラルキーに対する認知
- 2 階層の上昇移動を果たそうとする若者の努力及び葛藤
- 3 上昇移動のメカニズムに対する見方
- 4 小結
- 第4節 恋愛・結婚に関する読者の声の分析
- 1 恋愛・結婚に対する『中国青年』の態度及びその理想像
- 2 恋愛・結婚の投書から見る階層ヒエラルキーに対する認知
- 3 小結
- 第1節 1978−1984年における社会経済変動
- 第6章 階層上昇移動における金銭の役割への目覚め(1985−1991年)
- 第1節 1985−1991年における社会経済変動及び『中国青年』の変容
- 第2節 学業に関する読者投書の分析
- 1 大学受験に関する情報提供
- 2 進学結果をめぐる受験生の不安
- 3 大学進学のプレッシャーから来る中学生の心理的負担
- 4 教育達成で失敗した若者の向かう先
- 5 小結
- 第3節 職業をめぐる投書に見られる上昇志向
- 1 階層ヒエラルキーに対する認知
- 2 階層の上昇移動を果たそうとする若者の悩み
- 3 上昇移動の秩序に対する態度及び解釈
- 4 小結
- 第4節 恋愛・結婚に関する読者投書の分析
- 1 恋愛・結婚に関する『中国青年』掲載内容の特徴及びその立場
- 2 恋愛場面における農村出身というハンディ
- 3 経済収入の重視によって「時代遅れの兵隊さん」とされた軍人の悩み
- 4 出身家庭の社会的地位の違いに起因する恋の悩み
- 5 戸籍や出身など制度的要因による格差を超えていく高収入の魅力
- 6 小結
- 第7章 「個人奮闘」の時代という語られ方(1992−2000年)
- 第1節 1992−2000年における社会経済変動
- 第2節 個人の「成功」願望への注目
- 第3節 学業に関する読者投書の分析
- 1 幼児教育への目覚め
- 2 大学入試制度の不正利用に関する訴え
- 3 「世界で最も疲れる親」像
- 4 受験先生に苦しむ中高生の思い
- 5 教師と生徒の権力関係に関する悩み
- 6 小結
- 第4節 職業・自己実現に関する読者投書の分析
- 1 階層ヒエラルキーに対する認知
- 2 若者の上昇志向の在り方及びその悩み
- 3 階層上昇移動のメカニズムに対する解釈
- 4 小結
- 第5節 恋愛・結婚に関する読者投書の分析
- 1 恋愛・結婚に関する投書の概況
- 2 「お金に汚された本当の愛」との批判
- 3 金銭の重要性をめぐる若者のアンビバレントな気持ち
- 4 道徳的立場を強調しなくなる『中国青年』雑誌
- 5 小結
- 終章 欲望の理由
- 第1節 それぞれの時代の公的文化装置と生活世界の論理、及びその関係
- 1 1978−2000年における公的文化装置の変化
- 2 1978−2000年における生活世界の論理の変化
- 3 上昇志向をめぐる文化装置と生活世界の論理の関係
- 第2節 本研究の発見と課題
- 1 本研究の発見
- 2 本研究の意義と今後の課題
- 第1節 それぞれの時代の公的文化装置と生活世界の論理、及びその関係
- 第5章 教育達成による上昇移動への熱望(1978−1984年)
-
- 参考文献
- 索引
王鳳(Wang Feng)
中国山東省出身。浙大寧波理工学院外国語学部専任教員、副教授。社会学博士。山東師範大学で日本語を学び、北京外国語大学日本学研究センターで修士号を取得。NHK中国総局北京支局にて現地スタッフとして2年間勤務した後、立教大学社会学研究科博士後期課程に進学。島根県立大学北東アジア研究センター、浙江越秀外国語学院での勤務を経て、現職に至る。
序章 理由ある欲望
1 「欲望の氾濫」という道徳的な見地に立脚する批判的な見方
改革開放以降の中国の社会変動について、階層研究を始め多くの研究成果が蓄積されてきた。一方、社会の変動に伴う人々の意識の変化についての研究はさほど多くないが、中国の社会学者、周暁紅は改革開放30年来の「価値観及び社会の心態」の変化を「中国体験(china feelings)」と名付けた。この「中国体験」は、これまで「欲望の解放」による自我(ego)の拡張であると主に語られてきた。このような認識は多くの場合、否定的な意味合いを持っている。たとえば、このような見地に立ち、思想史の角度から「唯我的な個人主義」の由来について考察した文学研究者の許紀霖はそれを、「自我を中心とし、物欲を追求する、公共的責任を放棄した個人主義(egoism)」と描いた(許紀霖2009)。
マイナスな意味合いで価値判断が下されている許の上記の見解は、市場経済の称揚による消費主義的神話を内実とする「新イデオロギー」を指摘する文学研究者の王暁明などの中国の知識人の間だけでなく、改革開放後の中国社会に関心を持つ日本の研究者にも同様に見られる(王暁明2000)。「『唯銭一神教』の蔓延」や「『中国病症候群』の顕在化」、「国民総商人化」などの表現で改革開放後の中国の社会意識について指摘した日本の社会学者・菱田雅晴がその代表者の一人であろう。菱田は90年代の初頭より論文「鄧小平時代の社会意識」を発表し改革開放前後の中国の社会意識の変化に注目してきたが、2005年の文章で菱田は「欲望の認知、解放過程としてのチャイナ・ドリームの実現」によって、「社会主義に代わり『唯銭一神教』が新たな準拠枠となった…(中略)…『唯銭一神教』が完成し、無限定な欲望の解放がここからスタートし…(中略)…『国民総商人化』と称される社会的気風が醸成されるのも、人々の社会意識の中のエコノ・セントリズム=『唯銭一神教』のゆえであった』と指摘したうえで、中国の社会学者、邵道生の「社会心態危機」についての議論を引用し、中国の社会意識に存在する問題点に懸念を表明した(菱田・園田2005)。
このように、現代中国の社会意識について語る際に、「欲望の解放」による自我の拡張というマイナスな認識をもってする傾向が広まっている。社会意識の面から改革開放以降の中国を語る際に、「欲望の氾濫」という言葉が良く取り上げられ、また多くの場合、詳細な考察が伴わないまま、マイナスなイメージが付随している。そのような批判的な見方には、次のような論理が潜められている。即ち、市場経済の時代に入ってから、それまでの社会主義時代のように国家や社会など「公」の利益や「他人」の利益を考えるという利他的な生き方が失われてしまい、人々は自分自身の利益しか考えない「堕落した」人間になったという。このような善か悪かの二分法に立脚する道徳的な見地から下された批判的な見方では、この現象を市場経済の時代に入るにつれて人々の心に歪みが生じた結果だとして、現在の中国社会が「精神的困難」に陥っているという現状認識に立脚して、「価値観の立て直し」こそ問題の解決策になると主張している。
2 理由のある欲望という理解的な立場の可能性
「欲望の氾濫」と描かれたこのような現象を、本当にモラルの低下という個人の道徳的問題に起因すると捉えてよいのだろうか。
上記で述べた、人々の心は堕落したという批判的な見方は、もちろんありうるだろう。中国社会で実際に起こっているさまざまな社会現象を見れば、前の時代と比べると、確かに人々は自分の利益への追求をより積極的に、より赤裸々に表現ようになったと見受けられる。上記で述べた道徳的な見地による見方は、事実の一面、即ち、これまでの時代より、自分の利益への追求を表向きに出すようになったという一面を的確にとらえたと言えよう。しかし一方、このような見方をとることによって生じた限界もある。そこでは、道徳的な価値判断を下すことによって、現実を生きている一人ひとりの意識のさまざまな側面が不問とされてしまう恐れがある。なぜそのように自分の利益を積極的に求めるということを、表向きに出すようになったのか、また、表象としての欲望の後ろに隠されたのはどのような原動力があるのか、などの疑問に対する探求がそこで止ってしまうのである。
では、改革開放後の人々の欲望について、「心の歪み」「精神の困難」というふうに批判するのではなく、理解的な立場の存在が可能ならば、そこにはどのような「理由(わけ)」がありうるだろうか。
「文化装置論に何ができるか──人に努力させる仕組み」において奥村は、近代社会になってから、出身家庭の出自によって社会的地位が決まる属性主義として「である」原理は、業績によって社会的地位が決まる業績主義としての「できる」原理に取って代わったと指摘し、また、「生まれによる差別を排除したはず」の「できる」原理は、「「できる」かどうか一つで人を序列化」してしまうことにより、人々を努力させることができた」と指摘した(奥村1997)。この言葉から、「序列」=自分自身の社会的位置づけへの関心は、人々の欲望につながる可能性が示唆された。改革開放以降の中国では、経済体制の活性化と同時に、それまで政治的資源に加えて、教育的資源、金銭的資源による社会的上昇移動が可能となり、社会的地位をめぐる競争が活性化され、まさに「序列」の編み直しが始まったのである。その中で、人々は自分自身の社会的位置づけ=身分に対して、多くの希望と同時に、多くの不安も感じることとなるだろう。
従って本研究において、「欲望の氾濫」という言い方によって描かれた中国社会で起こっている現象を、人々の自分自身の社会的位置づけ=社会的地位に対する不安の、一種の副産物として理解できるのではないかと考えるようになった。そこでは、社会的位置づけの上昇移動を目指す意識、即ち上昇志向のあり方を究明すれば、「欲望の氾濫」と描かれるまで人々が自分自身の利益に対する追求が過熱化されているという社会現象がなぜ起こるのかとの問いに近づけるのではないかと考えている。
3 公的文化装置の論理と生活世界の論理
本研究において社会的位置づけの上昇移動に関する意識=上昇志向について考察する際に、政治社会から脱皮してきた中国社会であるからこそ、人々の意識や行動に対して多大な影響力を持つ文化的構築物=文化装置という要素の存在が大きく考えられよう。
そして、公的文化装置の論理を取り立てて考えることによって、その対置にある人々の自分自身の体験に基づき感知した生活世界の論理というもう一つの世界も浮かび上がってくるのである。本研究では、この二つの論理について同時に視野に入れて考えることによって、改革開放以降の中国社会を生きる人々の意識に近づきたいと考える。
以下では、ミルズの文化装置論とアルチュセールの理論である「国家のイデオロギー装置」を踏まえて、本研究の分析枠組みである文化装置論と生活世界の論理を説明する。
ミルズは、文化と政治の関係や文化に関する政治について論じる際に、文化装置という言葉を分析の道具として提起した。ミルズの言葉を借りて文化装置を紹介すると、人間の意識とかれらの物質的存在との間には、存在に関する人々の意識に決定的影響を与える解釈、というものがある。この解釈の仕組みを用意するものは、文化装置である。文化装置の内部で、人間と出来事の間にあって、人間の生きる世界を限定するイメージや意味やスローガンが組織されたり、比較されたり、維持されたり修正されたり、また消滅、育成、隠蔽、暴露、称されたりする。文化装置の中で、芸術、科学、学問、娯楽、笑話、情報が生み出され分配される。それによって、これらの生産物は分配され、消費される。それは、学校、劇場、新聞、人口調査局、撮影所、図書館、小雑誌、ラジオ放送網といった複雑な一連の諸施設をもっている(Mills 1959=1984)。
このうえで、ミルズは次ぎのように文化装置を定義した。「全体として考えると、文化装置は人々がそれを通して見る人類のレンズであるといえよう。人々はその媒介によって自分たちが見るものを解釈し報告する。それはかれらの同一性と願望の半ば組織された源泉であり、人間の多様性──生き方と死に方──の源泉でもある」と(Mills 1959=1984)。
また、ミルズの文化装置理論を用いて高度成長期の日本社会の「加熱する文化装置」について分析した奥村隆は、次ぎのように文化装置について説明した。人間は、個人的に直接経験するよりずっと多くのことを知っており、ほとんどの経験が、何か媒介された間接的な経験と言っていい。またどんな経験でも、ある解釈をして経験するのであり、その解釈の仕組みは、自分自身が作ったものではなく、他人から引き継いだものである。そうした間接的な経験を伝達するもの、解釈の枠組みを用意するものを「文化装置」という(奥村1997)。
まとめると、ミルズの言った文化装置は、「ひとが何かを見るためのレンズのようなもの」であり、「ひとが見ているものを解釈し、報告するために用いるメディア」を指す。また、それを通して私たちが社会的な経験(出来事/事件)を意味づけ、理解し、解釈するための媒介として文化的構築物であると言えよう。
一方、人々の意識を形づくる文化的構築物の存在について、アルチュセールは、「国家のイデオロギー装置」との概念を提起した。アルチュセールは、「生産諸関係の再生産はいかにして保証されるか」(Althusser 1995=2005:340)について検討する際に、「生産諸関係の再生産は、きわめて大きな部分が、一方におけると他方におけるというにおける国家権力の行使によって保証されている」(Althusser 1995=2005:340-1)と述べた。アルチュセールによれば、国家(の抑圧)装置は政府、行政機関、軍隊、警察、裁判所、刑務所など「暴力的に機能する」ものを指すのに対して、国家のイデオロギー諸装置は宗教、学校、家族、新聞やテレビなどのメディア、文学や美術のような文化的産物など「イデオロギー的に」機能するものを指す*1(Althusser 1995=2005:335-6)。
アルチュセールの文脈でいうイデオロギーとはどのようなものであろうか。「イデオロギーと国家のイデオロギー諸装置」という論文の中でアルチュセールは、イデオロギーについて「一人の人間、或いは社会的な一集団の精神を支配する諸観念や諸表象の体系」というマルクスの定義を引用したうえで、イデオロギーと「人間の存在の現実的諸条件」との関係性では、「純粋な幻想、純粋な夢」、「空想的な構造物」であり、「想像的なでっち上げであり、物質的に自己の存在を生み出す具体的で物質的な諸個人の具体的な歴史の現実である、あの充実し実在する唯一の現実の、『昼間の名残り』によって構成された、空虚でむなしい、全くの夢」であるというマルクスの見方(Althusser 1995=2005:351)に対して、アルチュセールはイデオロギーの物質性を強調し、「諸個人が自らの現実的な存在諸条件に対してもつ想像的な関係の「表象」である」と定義した(Althusser 1995=2005:353)。そのうえ、次ぎのように指摘した。すべてのイデオロギーは諸制度の中で、それらの制度の儀式と実践を通して、「呼びかけ(interpellation)」という物質的実践によって具体的な諸個人を主体として構築する。イデオロギーは、物質的なイデオロギー装置の中に存在し、この装置は物質的な儀式によって調整される物質的な諸実践を命令し、これらの諸実践は自己の信仰に従って全く意識的に行動する主体の物質的な諸行為の中に存在する(Althusser 1995=2005:362)。このように主体を構築することによって、国家のイデオロギー装置は既存の権力システムの再生産に協力する。
以上では、ミルズの文化装置論とアルチュセールのイデオロギー装置に関する説明を見てきた。
では、本研究にとって、ミルズの「文化装置」との概念、アルチュセールの「国家のイデオロギー装置」との概念の意味は、どこにあるだろうか。
ミルズは「文化装置」という概念を用いることによって、さまざまな社会段階や違う社会における一見して必ずしも政治と関係していない文化の政治性を暴いた。またアルチュセールは、「国家のイデオロギー装置」という概念を用いることによって、生産諸条件の再生産に対して、国家のイデオロギー装置による主体の構築という過程の不可欠さを強調した。二つの理論はそれぞれ違う学術的文脈があり着眼点も大きく違う。一方、文化装置によって提供される解釈の枠組み、国家のイデオロギー装置によって提供されたイデオロギー、この二つの理論で共通する点をまとめると、人間の意識形成に重要な影響を与えるものとして、「人間と出来事の間にあって、人間の生きる世界を限定する」解釈の枠組、「諸個人の存在の現実的諸条件」に関する「想像」といったような文化的構築物があると言えよう。個人の内面の意識に近づくには、この文化的構築物に対する考察が非常に重要であろう。
一方、「諸個人が自らの現実的な存在諸条件に対してもつ想像的な関係の「表象」である」というアルチュセールによるイデオロギーの定義を考える場合に、具体的な個人にとって、「自らの現実的な存在諸条件に対して持つ」想像は、国家のイデオロギー装置や公的文化装置に規定されるもの以外に、人々が自分自身の生活経験から感知したことによって、公的イデオロギーとは別のイデオロギーや想像を形成させることもありうるだろう。本研究において、人々が自分自身の生活体験に基づき形成された、「自らの現実的存在諸条件」に対して持つ想像を、生活世界の論理と呼ぶ。
では、1978年以降の中国社会の人々の意識の変化について考える際に、公的文化装置の論理と生活世界の論理という分析枠組みの有効性は、どこにあるのだろうか。
本研究は、1978年の改革開放以降の中国社会で起こった、「欲望の氾濫」と言われるさまざまな個人利益の過剰なまでの主張という社会現象がなぜ起こっているのか、人々の社会的位置づけの上昇移動を目指す上昇志向を考察して社会学的に理解しようとするものである。
今まで、この問題に対する答えとしては、これまでの社会意識研究の成果を見通すと、人々が行動時に依拠する準拠枠の変化に原因を求めるのが代表的な立場である。改革開放政策によって欲望の認知・解放が起こることによって、これまで準拠枠としての社会主義イデオロギーという文化的構築物がその機能を喪失し、唯銭一神教=拝金主義が変わりに新たな準拠枠となったというのが一般的である(菱田2005)。この文脈で、「公的価値から私的価値へ」、「私的領域への逃避傾向」などの言葉がよく提起される。また、この延長線上、人々の道徳水準の下落などいわゆる「精神の危機」という個人のモラルの問題が提起される。
準拠枠の変化やモラルの問題に原因を求めた上記の結論は、確かに1978年以降現在までのある中国社会の変化を素描したと認めていいだろう。しかし一方、この変化は、人々に対して誘導を試みてきた公的イデオロギー=社会主義的準拠枠による人々への拘束性の弱まりを意味するに過ぎないとここで指摘したい。前述の理論的考察を想起すると、これは、人々に対して絶えず発信する政治的な文化構築物の変化であることが分かるだろう。
しかし一方、筆者が個人の体験で感知したように、公的イデオロギーの拘束という要素以外に、個人の内部で何が起こっているか=生活世界における人々の現実に対する認識や感知をベースとする社会のあり方に関する想像、というものもある。実際の生活の中で、この想像は立派なイデオロギー/解釈の枠組みとなり、人々の行動の準拠枠となっているのである。
よって本研究では、人々の意識に近づくためには、公的イデオロギー=国家のイデオロギー装置の提供する存在に関する解釈の枠組みを公的文化装置として重要な位置づけにあると認めながらも、それのみならず、人々が現実世界に対する認知や感知に基づいて形成された彼らなりの世界観=彼ら自身の人生体験に基づく存在に関する解釈の枠組みという、もう一つの要素があると提起したい。即ち、改革開放以降の中国社会を生きる人々の意識に近づくには、国家のイデオロギー装置の提供する解釈の枠組み=公的文化装置の論理と、人々が自身の体験に基づいた解釈の枠組み=生活世界の論理という二つの要素を、同時に視野に置いて考察する必要があると指摘したい。
そのために、本研究では文化装置という概念を導入することによって、人々の意識を観察する上で既存研究で強調されたた公的イデオロギーの変化を一つの重要な要素として認める。と同時に、公的イデオロギーの変化=文化装置の内容の変化はあくまでもの重要な要素の中の一つにすぎず、これ以外に、人々が自身の体験に基づき形成された解釈の枠組みという要素も重要だと強調したいのである。
便宜上、以下では、公的・社会的イデオロギー装置によって提供された解釈の枠組みを文化装置による公的文化装置の論理と呼び、人々が自身の人生体験に基づいた現実世界に対する解釈の枠組みを生活世界の論理と呼ぼう。文化装置による公的イデオロギー及び生活者の想像の内実を、『中国青年』という雑誌の内容に関する分析を通してアプローチしていきたい。
4 研究目的:二つの理解
では、人々が過度なまでに自分自身の利益を求めるようになり、またそのような意図に対して隠すのではなく、表向きに出すようになった現象について、もし「欲望の氾濫」という批判的で閉鎖的な見方ではなく、自分自身の社会的位置づけの不安という理解のまなざしを向ける際に、どのような風景が見えてくるのだろうか。
ここでは、人々が生活世界の中で感じた出自家族や自分自身の社会的位置づけに関する不安から来る上昇移動の衝動と、人々を取り巻く文化装置のあり方という二つの点を同時に視野に入れ、改革開放以降において、この二つの点がそれぞれの時期においてどのような関係性を持っており、どのような過程を経て、現在「欲望の氾濫」と呼ばれるような現象が現れるようになったのかを考察したい。また「欲望の氾濫」という言い方に対しても、その背後にどのようなイデオロギーを持っており、どのような社会的背景があるのかとの問いにアプローチして相対化の作業を行いたい。
総じていえば、本書を通して行うことが基本的に二つある。さらに言えば、二つのことに対して、理解を試みるのだ。
第一に、「欲望の氾濫」と言われた改革開放後の中国社会を生きる人々の意識の有様について、「心の歪み」「精神の困難」などの言葉をもってこれは間違った生き方だという批判的な視線を超えて、理解的な立場をもって、その理由(わけ)を究明したいというのが基本的な立場である。人々が実際の生活世界で自分自身の社会的位置づけに対してどのような不安を持ち、どのような欲求を充足したくてそのような現象につながったのか、即ちその背後の理由にアプローチしたい。よって、本研究のひとつの目的は、人々は自分自身の社会的位置づけ=社会的地位の上昇移動を目指す上昇志向のあり方という点に焦点を当てることにする。改革開放以降において上昇志向をめぐる生活世界の論理を時代ごとに考察して究明する。
第二に、「欲望の氾濫」という道徳的判断を一種の「文化装置」=ある現象に対する応急反応/防衛反応として見る。「欲望の氾濫」という評価の仕方の背後にあるイデオロギーが、文化装置として、どのような社会的背景があり、どのようにしてそれが可能となったのかを考察する。改革開放以来、時代が下るにつれて、これまでに何種類かの文化装置が出回った。改革開放以降における社会主義イデオロギーとの政治的流れを汲んだある公的文化装置の、社会のあり方に対する解釈の変化の過程を描き出すことによって、こういった道徳的判断も、一種の歴史的産物としてとらえなおすことができ、その絶対性を脱構築するができる。その生まれる歴史的背景を明るみにすることによって、なぜその時期にそのような見方ができたのかを究明して、それに対する理解が可能となるだろう。
5 研究方法と研究枠組の進み方
具体的には、改革開放以降の人々の上昇志向について、1978~1984年、1985~1991年、1992~2000年という三つの時代区分をした上で、それぞれの時期に人々はどのような上昇志向を持っており、またその時代の公的文化装置はどのような様相を呈していたのか考察したい。以上の問題意識を解明するためには、本書は、1978年~2000年の『中国青年』雑誌を研究対象として選定した。そこで行われている作業は、主に次の二つである。
一つ目に、1978年から始まった路線転換以降の中国社会において、文化装置としての公式見解がその時代の社会のあり方についてどのように解釈して、人々の、社会的地位の不安を解消するためのエネルギー=上昇志向についてどのようにして方向付けようとして、またどのように規制していたのかについて分析する。これは主として雑誌の特徴的なコラムの内容分析、表紙の考察などを通して行う。1978年以来、『中国青年』雑誌は政治的色彩の強い機関誌から徐々に文化総合誌に脱皮していったが、その中で、雑誌が読者に提示した社会のあり方の解釈枠組みも何度か変化した。雑誌の表紙や主要コラム、雑誌の位置づけなどについて考察することによって、その時代において人々が身を置かれている社会のイデオロギー、社会的雰囲気=文化装置を明らかにする。
二つ目に、社会・経済的状況が変化していく中で、それぞれの時代の中で人々はどのような上昇志向を持っており、自分自身の社会的位置づけに関してどのような不安に直面していたかを究明する。これは、主として『中国青年』雑誌の投書欄に掲載された投書を資料にして行う。人々が生活世界で何を感じてどのような欲求を充足したいのかを反映する投書を代表とする読者の声を考察し、そこで浮かびあがってくる人々の意識に接近する。
読者の声に対する考察は、具体的に以下の三つの点を中心に進めていく。
第一、階層ヒエラルキーの存在に関する認知はどのようなものであるか。
第二、どのようにして上昇移動を果たそうとして、そしてどのような悩みを持っていたか。即ち、人々にとっての階層の持つ実存的意味とはどういうもので、上昇志向のあり方はどのような様相を呈しているか。
第三、上昇移動のメカニズムや社会秩序のあり方に対してどのような解釈・想像を持っていたか。
本書の構成は大きく二部に分かれている。
第一部は序章から第四章まで計五つの章からなっており、それぞれの内容は下記の通りになっている。序章では、本研究の問題意識と研究枠組みについて説明する。第一章では、改革開放以降の中国の社会意識の究明に役立つ先行研究のレビューをする。第二章は、1978年以降の中国雑誌業界における『中国青年』雑誌の位置づけと特徴、及び本研究で主な資料として利用される読者の声の抽出の方法について説明する。第三章では、1978年以降の中国の社会経済変動について概観する。第四章では、1978年復刊してから2003年まで、『中国青年』はメディアとしてどのような変化を遂げ、特にそのキャッチフレーズの変化を通して社会的イデオロギーの流れを汲んだ中国社会にある一つの公的文化装置の変化の見取り図を整理する。
第二部は第五章、第六章、第七章、終章という四つの章からなっている。第五章、第六章、第七章では、それぞれ1978~1984、1985~1991、1993~2000という時代区分ののもとで考察を進めていくが、雑誌に掲載された読者投書に注目して、その時代において人々が自分自身の位置づけや上昇志向について実際にどのように感じているのかを考察する。終章では、以上の考察をまとめる。
注
*1: さまざまな国家のイデオロギー諸装置の中でアルチュセールは、かつての時代において教会が支配的なイデオロギー装置であったのに対して、「成熟した資本主義的構成体において支配的な地位を占めるに至ったは、学校的イデオロギー装置なのである」と言い、近代に入ってから、学校装置の支配的役割を強調した。
- 欲望 11
- 階層研究 11
- 中国体験 11
- 社会意識 12
- 文化装置論 13
- 社会的位置づけ 13
- 階層の上昇移動 13, 200, 241
- 上昇志向 13
- 新イデオロギー 34
- チャイナ・ドリーム 34, 41-43
- 欲望弁証法 39
- 階層意識 44-49
- 社会秩序に関する解釈と想像 49, 159
- メリトクラシーしゃかい 49, 51
- 選抜システム 49
- 立身出世 50
- 属性要因に差別 50
- 『中国青年』雑誌 57-88
- 市場化 77
- 読者投書 77, 158
- 学業に関する読者投書 158, 200, 423
- 職業に関する読者投書 203, 241
- 恋愛・結婚に関する読者投書 242
- 大学入試制度の再開 153
- 教育達成 153, 208
- 四つの現代化 158
- 階層ヒエラルキーに関する認知 159, 200, 202, 241, 276, 286, 306-309, 373-375, 409, 424, 448-449, 559, 574-584
- 上昇志向のあり方 159, 200, 241, 285, 373-375, 409, 424, 448-449, 467, 520, 538, 559, 574, 578-581
- 上昇移動のメカニズムに対する解釈 200, 241-242, 286, 306-309, 373-375, 409, 424, 448-449, 520, 537, 539, 559, 574-581
- 個人奮闘の時代 417
- 市場経済化 417
- 高等教育の大衆化 418
- 個人の「成功」願望 419